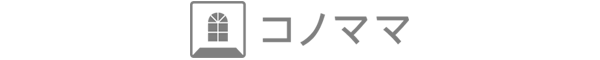人間の霊魂と同じようなものが広く自然界にも存在するという考え。自然界にも精神的価値を認めこれを崇拝する宗教の原型のひとつで、世界各地でみられた。今日でも、各地域の先住民の間で現存し、また、さまざまな宗教や民俗、風習にもその名残がある。(中略)今日の自然保護思想のうえで、アニミズム的な感覚や発想を再評価する動きも起きている。
EICネット 一般財団法人環境イノベーション情報機構
アニミズムの世界
ハワイには「すべてのものに精霊が宿っている」という考え方があり、フラダンスはそれらへの感謝の気持ちを表した踊りだと言います。同じような思想はバリ島にもあり、私は友人宅で水、火、鉄・・・といたるところに宿る神にお供え物をする儀式を教わりました。日本でも「森羅万象に神霊が宿る、森羅万象が霊魂を持つ」と信じられていたと聞きます。




昨今の日本のアニメは、ジブリ映画に代表されるようにアニミズム的な世界観が描かれているものが多いように思います。そういった作品が子供にも大人にも、日本でも海外でも人気を得ているのを見ると、人間が持つ自然や物、動物に対する畏敬の念というものは、宗教や文化に関係のない本能的なものなのではないかと思えます。

アニミズムを感じる実写映画
私がアニミズムを感じた4作品です。どの作品でも精霊や霊魂、動物の心といった実体のないものが表現されています。
クジラ島の少女(ニュージーランド)
古い伝統に新しい息吹をもたらした少女の信念に、感動と力をもらいます。
ラグビーのニュージーランド代表によって日本でも人気となったハカ。ハカは先住民であるマオリ族の民族舞踊ですが、この映画はそのマオリ族の話です。
その昔クジラに乗ってやってきたというマオリ族。族長は村民が伝統を重んじる気持ちを失くしていることを危惧し、人々を救う次なる指導者のことばかり考えています。代々男性が族長となることを承継してきた一家ですが、長男は使命に背き、期待した孫は女の子でした。しかし、伝説の勇者パイケアの名をもらったその女の子は、誰よりも熱心に伝統を学びます。厳格な族長も祖父としてはパイケアを可愛がりますが、パイケアが無邪気に男性の世界へ入ろうとすることには非情なほどに怒ります。傷つきながらもパイケアは一途な思いを持ち続け、そしてついにはクジラと心を通わせます・・・
パイケアの健気な姿に感動すると同時に、周囲の人々の優しさにも心打たれます。中でも存在感を示すのは女性たちです。顕著な男社会の中で夫に真っ向から反発したり、恋人にはっぱをかけたり、小気味よく旧来の教えを破ったり、彼女たちの言動こそ力強く頼もしいのです。
同じポリネシアンを舞台としたディズニー映画『モアナと伝説の海』を観た時に、この『クジラ島の少女』を思い出しました。同じようなメッセージを持った映画です。


ブンミおじさんの森(タイ)
日本人にも共通する死生観が、観る人を穏やかな気持ちにさせてくれます。
タイの田舎で暮らすブンミの家に、ある日亡くなった妻が現れ、続いて行方不明になっていた息子が猿の姿になって現れます。ブンミも義妹たちも怖がったり感傷的になったりせず、ごく自然に彼らと一緒に食卓を囲みます。死期が近いことを悟ったブンミが自分の前世を思い出したり、未来を見るシーンでもまた、輪廻転生が淡々と表現されています。終盤は一変して都会が舞台となり、ブンミの死後に出家した青年の様子が描かれています。彼は典型的な現代っ子ですが、彼の身にも幽体離脱のような現象が起こります。こういった不思議なことを日常風景のように描いているところが、この映画の独特なところであって魅力です。
ブンミは死によって生まれ変わりを繰り返していますが、息子が猿の精霊になったり王女がナマズになったり、今生での生まれ変わりもテーマとなっています。青年の出家もある意味の生まれ変わりです。生と死、生まれ変わりといった大きなテーマがゆったりとした流れで描かれていて、不思議と穏やかな気持ちになります。
いろいろな場面で神秘的な青色が印象深く残りました。冒頭、牛のシルエットを浮かび上がらせる青い背景。王女が身を浸す水の青。洞窟の外に見える青。そして森の中も全体的に青みを帯びて映し出されます。静謐な作風にとても合っています。

ミツバチのささやき(スペイン)
言論の自由さえ奪われた時代に、監督がこの映画に込めたメッセージが心に沁みます。
独裁政権となって自由が失われた1940年代のスペインが舞台です。幼い姉妹のアナとイザベルの周りでも、大人たちは不安や悲しみを抱えて生活しています。そんな中、映画で観たフランケンシュタインが気になるアナは、姉イザベルの嘘をきっかけに廃屋に足を運ぶようになります。
ある日の学校、人間の器官について学ぶ授業で、人形に足りていなかった“目”を当てはめるアナ。先生は「これでドン・ホセ(人形の名前)は見えるようになりました」と言います。そして感受性の鋭いアナもまた、その目で様々なものを見ていきます。父親が踏みつぶす毒キノコや近付いてくる汽車をも、アナはなにかを思うようにじっと見つめます。傷ついた兵士とは心の交流も生まれます。そして夜中に家を抜け出して向かった先では・・・
子供のために働き続けなければいけないことを憂いているような父親のモノローグがありますが、仕事机には子供たちを思わせる折り紙が2つ置かれています。時代に引き裂かれた男性を想い夫には愛情がないように見える妻ですが、夫が机で眠ってしまった時にはそっと労わります。働き蜂と自分たちの生活を重ねる父親のモノローグや、時折クローズアップされる宗教画に重苦しい情勢を感じますが、そんな暗澹とした生活の中に見える家族愛に希望も感じます。
アナを診察した医者が母親に、「アナは生きているんだ。大切なのは生きているということだ。」と伝えるシーンがあります。この作品で監督が言いたかったことではないでしょうか。
アナのまっすぐな眼差しが印象深く忘れられません。

ふたり(日本)
おっとりした少女の強さは、目の前の状況を受け入れる柔軟な心と想像力だと思います。
大林宣彦監督の「新・尾道三部作」の1作目です。
優秀でしっかり者の姉・千津子と、ドジで空想好きの妹・実加。突然の事故でこの世を去った千津子は、その後も幽霊となって実加の前に現れて頼りない妹の支えとなります。これぞファンタジーというような設定ですが、学校での嫌がらせや家庭の不和など、厳しい現実を乗り越え成長していく実加の姿にはリアリティを感じます。昔の青春ドラマのような気恥ずかしくなるシーンがある一方、大人になった今でも心に響くセリフがあります。まるでアンバランスな思春期のように、この作品自体が相反する要素を持ち合わせているところが魅力となっているのです。
そして考えるのは、まるで反対の性格を持つ千津子と実加の生命力です。千津子の死はあくまでも不慮の事故ですが、しっかり者の千津子は人知れず弱さも抱えていました。一方、実加は劣等感の強い少女ですが、いつしか自分らしい居場所を見つけ、自分の人生を生き始めます。姉と同じ主役を演じるはずだった演劇部の発表会では部員の嫉妬から裏方に回されますが、置かれた場所に意味を見出す力を実加は持っていたのです。
尾道の風景と久石譲の音楽はどこか懐かしく、それも相まって確か初めて好きになった邦画です。後に、映画を一緒に観た友人と尾道へ旅行するきっかけとなりました。