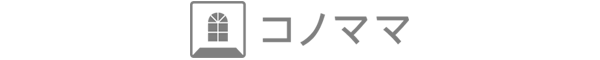映画『ノマドランド』と親の終活を見て、自分らしい生き方というものを考えさせられました。生き方は時間の使い方。若い頃はもっと時間があったはずなのに、いつからか光陰矢の如しで、時間が有限であることを思い知らされます。これからは自分の人生に必要なものを取捨選択し、優先順位をつけ、好きなことにたっぷりと時間を費やすような過ごし方がしたいものです。
『ノマドランド』に思う、大切にしたいこと
主人公のファーンは放浪民、いわゆるノマド的な生活をしている61歳の女性。家を持たず、短期労働で収入を得ながら車上生活を送る、そのリアルな日常を描いたドキュメンタリーのような作品です。監督が中国人の女性だと知って正直なところ意外に思ったのですが、それもまた今という時代を象徴しているように感じました。
今という時間をどう過ごすか
ノマドとして生きる高齢の単身者たち。その役で出演するほとんどの人が、実際にノマド生活を送っている一般人です。ファーンをはじめその何人かは、ベトナム戦争や2008年の金融危機といったことに端を発してノマドという生き方を選んでいます。ニュースでは見えてこないアメリカの実状、ともすると多くの国の“これから”なのだろうと思います。近年の社会的なことが背景にあるという点で、自分と無縁ではない身近な話に感じられました。
星を観測しながら「24年前の光が今届いている」といったことを話すシーンがあります。星の光が届くまでの時間というと何億年というスケールの時間が示されてロマンチックに語られることがありますが、24年とは妙にリアルです。そのためここでも月日の流れというものが意識され、過去と現在と未来は連続しているという当然の理を再確認させられた気分になりました。
数十年前の社会的な出来事、あるいは自分の選択が今に繋がり、今が未来を作るのです。


自分で意思決定する
今はノマドのような働き方や暮らし方がブームのようになっていますが、それもひとつの選択肢です。この映画に出てくる人たちは、ある時点ではその生き方しか選べなかった人もいますが、違った道が目の前に開かれる場合もあります。ファーンの場合もそうで、彼女を心配する人たちから同居を提案されますが、その度に彼らの誘いを断ってノマドという生き方を続けます。
一方で、ノマド生活を止め息子夫婦の家で暮らし始める仲間もいます。その後押しをしたのは他でもないファーンの「考えすぎないでお父さんをやって」という言葉。父親としての自信がなかった彼も、自分で選択したその後の暮らしに幸せを感じているように見えました。
訪れた機会に委ねるのも拒むのも、人の意見を受け入れる決断も反する決断も、自分の意志によるものだから納得できるのでしょう。


人と繋がる時間と自分だけの時間
ノマド生活を送る人たちが集うイベントがあります。彼らはそれぞれに旅を続けながらも繋がりを持ち、助け合いながらその生活を続けているのです。そのイベントの主催者の言葉には、多くのことを経験してきた人の重みと優しさがあります。「最後の“さよなら”がない。“また路上で会おう”と言って別れ、実際そうなる。また会える。」人との繋がり方をそう話します。「死ぬ時に後悔するな。」仲間にそう語る場面もあります。
ストーリーの中でひとりの仲間が最期を迎えますが、彼女は余命が幾ばくも無いことを知りながら旅を続け、目指していた思い出の地に辿り着いたことを友に報せます。孤高とも言える旅と、それを尊重しあう仲間と、どちらも彼女にとって大切なものだったのでしょう。旅の途中、ファーンの前で「いい人生だった。」と振り返ったように、きっと最期もそう思ったのだろうと想像します。


それぞれの価値観と考え方
この映画からは本当にいろいろなことを感じるし、観る人によって受け取り方は様々なのだろうと思います。きっとノマドという生き方を哀れむ人もいれば羨む人もいると思いますが、私には、それぞれ悲しみを抱えながらも自分の思いを大切にしている生き方のように見えました。
世の中には“他人から幸せそうに見える方”を選ぶ人もいますが、ファーンやその仲間は自分の価値観に正直です。劇中の言葉を借りれば、“ハウス”は持たず“ホーム”を大切にしている人たちであり、“経済”という沈みかけているタイタニックからいち早く逃げ出した人々です。ファーンの姉が言ったように“開拓者”なのかもしれないし、ファーンが自分の車に名付けた通り“先駆者”なのかもしれません。



映画を観終えた後も、表情豊かなアメリカの自然ともの悲しい音楽が心に残ります。対照的にノマドという生き方自体は淡々と描かれ、観る側に考える余地が与えられています。そのため夫の観点は私とまったく異なるもので、深い洞察がとても面白いです。
終活に思う、自分らしさ
私の父はエンディングノートを遺しました。健康なうちから書き始め、内容に変更があれば更新し、晩年は常々私たちにその内容を説明していました。それだけでなく終末期の医療に関する意向書を書き、年賀状じまいをし、遺影を用意し、棺桶に入るという体験までして、いわゆる終活を着実に進めていました。この在り方、几帳面だった父の性格をとてもよく表しています。
亡くなる1年前、空き家となって片付けに困っていた生家を思わぬ縁から売却することができ、翌年にはその確定申告を済ませ、全てを綺麗に片付けた直後の往生でした。最後の1年はまるで父の性格に合った道筋が用意されていたように感じましたが、本人にとっては自分で思い描いた誇らしい幕引きだったのだと思います。どういう終わり方をするか。何事も引き際にその人らしさが表れると、改めて思いました。

私もある程度の年齢になったらエンディングノートを書こうと決めています。自分と向き合うにはこの上ないツールであり、考えが整理されて有意義な余生を送れる気がするので、今からその時が楽しみです。また父の遺影を見たら、元気なうちにプロに撮影してもらわない手はないとも思っています。なんせ父は、実物の印象からは程遠い素敵な老紳士に写っていたのですから。遺影を含め自分の祭壇を自分でデザインできたなら、それは確かに本望です。